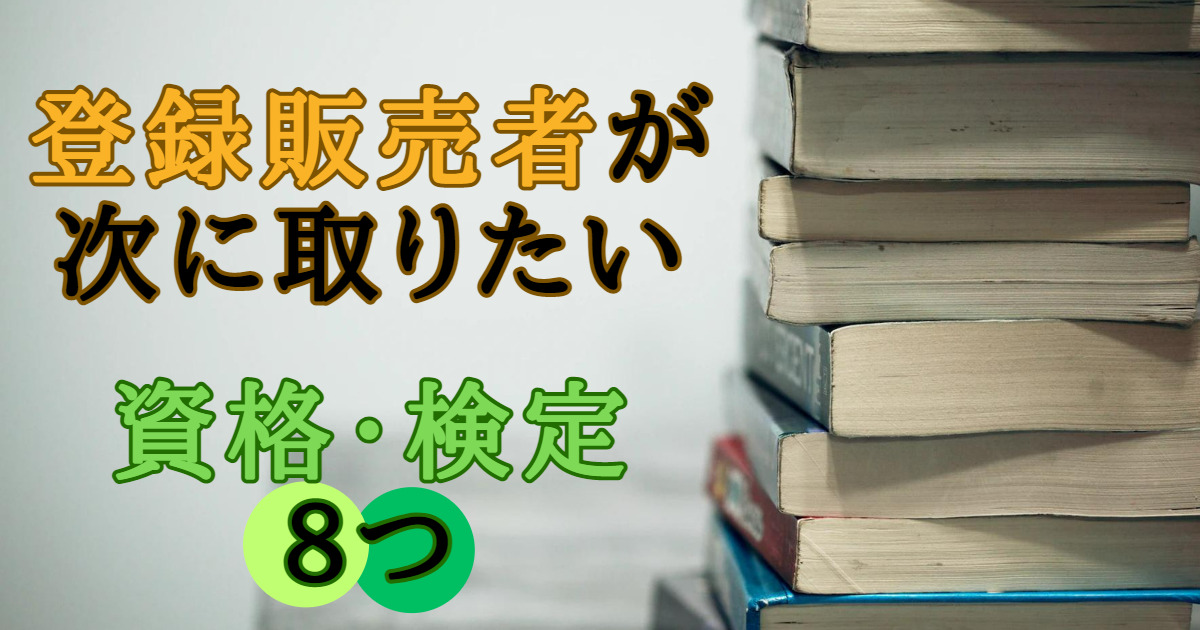登録販売者のへむぅです。私は2020年の12月に登録販売者を受験し、一発合格しました。
しかし、今は登録販売者の仕事には就いていません。せっかくなのでこの機会に、登録販売者に関連する次に取得したい資格や検定をランキング形式で紹介いたします。

このランキングは独自のものです。
少しでも参考になればうれしいです!
関連する3つのジャンル
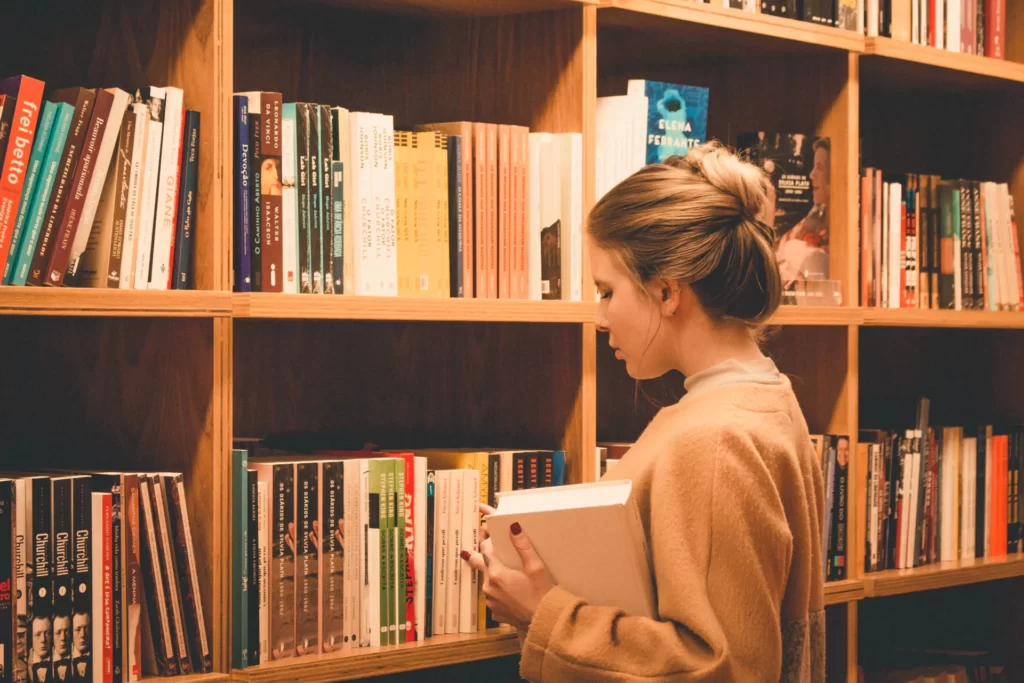
登録販売者が今後取得する資格検定は、いくつかのジャンルに分かれていると考えます。
私の思うジャンルは、【東洋医学・ドラッグストアで役立つ・その他】の3つです。ひとつずつ見ていきましょう。
東洋医学系の資格・検定
第三章ではなにかとカタカナの成分名と生薬・漢方が多いイメージの登録販売者試験ですが、後者の生薬・漢方は東洋医学に含まれます。
漢方分野の手引きの中で、東洋医学を説明するこんな文章があります。
漢方の病態認識には虚実、陰陽、気血水、五臓などがある。
厚生労働省‐登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)
虚実に関しては、漢方薬を覚える際に「体力虚弱で~・・・」など度々出てきたので少しはイメージできるかと思いますが、他はいかがですか?
気血水や五臓のことには、登録販売者試験では触れません。それを深く学べる東洋医学の資格・検定も興味深いですね。生活に役立つことが知識として身につくため、私が学びたい分野のひとつです。
東洋医学系の資格・検定は、多々ありますが、ここでは以下2つ。
- 中医学検定
- 薬膳・漢方検定
ドラッグストアで役立つ資格・検定
ドラッグストアにはよく行きますか? 私は週に1度は行きます。薬はもちろん、食品やペット用品などたくさんの種類のものが陳列されていますね。
中でも薬以外で注目するのは化粧品・サプリメントの二つです。化粧品もサプリメントも、様々な種類があり、そして成分があります。
日常で化粧品の裏面の成分欄を見てみると、登録販売者試験で覚えた成分名もあれば、全く見たことのない成分もあります。
化粧品の知識も今のままでは足りないかもしれません。サプリメントも同様です。さらに成分名等を覚えて、接客や生活に役立てるのも良いですね。
化粧品とサプリメントの資格・検定は、代表的なもので3つ挙げられます。
- 日本化粧品検定
- 化粧品成分検定
- サプリメントマイスター検定
その他:薬学系や調剤事務、アロマなど
最後はその他。
考え方・登録販売者の資格との繋げ方・自分が今後どうなっていきたいかによって無数の資格・検定があるかと思います。
薬の知識をもっとつけたいのであれば、薬学に関すること。
登録販売者として調剤事務で働きたいのであれば、調剤事務の試験。
香りの力を心身の不調に活かすにはアロマテラピーを学ぶことも考えられます。はたまた、介護士や栄養士・薬剤師など公的な資格を取る道もあります。
今回は私独自のランキングということで、その中から3つ。
- 薬学検定
- 調剤報酬請求事務技能認定
- メディカルアロマ検定
取得したい資格・検定ランキング!
このランキングはあくまで著者の主観で決めたものです。ご自身の興味や働き先、将来どうなりたいかにより変わるものかと思います。

こんな検定があるんだ!

へぇ、考え方次第だな~
そう思っていただければ幸いです。それでは、ランキングスタート!
第8位:調剤報酬請求事務技能認定
調剤事務の仕事で役立つ資格です。
【調剤報酬請求事務技能認定】の試験は、ニチイが開講している調剤事務の講座を受講後、認定が受けられます。名前は違えど、調剤報酬に関して学べる試験や講座はいくつも存在します。内容に大差はないように思います。
この資格を私は登録販売者試験の合格後に取得しました。当時は調剤事務の仕事をしていたのですが、「必ず役に立つ!」とは思いませんでした。
確かに学べる箇所はあります。なぜこのような金額・点数になるのかが理解できるので自信をもって調剤事務の仕事ができます。
しかし、現在では多数の調剤薬局がレセコン(レセプトコンピュータ)というものを導入しており、手入力や自力で計算することがありません。自動でやってくれるのならば、時が戻るのなら他のことを勉強したいなと考えます。
登録販売者兼調剤事務の仕事をするのならば、調剤事務の仕事に自信が持てる!
第7位:日本化粧品検定
化粧品・美容に関する知識の普及と向上を目指した検定です。
ドラックストア勤務であれば、登録販売者兼コスメ販売員(美容部員)として活躍できる!
日本化粧品検定は3級・2級・1級・特級と4つの階級にわかれています。1級に合格後特級に申し込み、講座や試験を受けると特級コスメコンシェルジュが取得できます。
調剤事務の先輩で特級コスメコンシェルジュの方がいました。化粧品のことを聞けば詳しく教えてくれ、知識の幅がすごかったです!
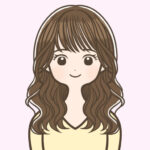
取得すれば、自分が化粧品を選ぶのも楽しくなりそうですね♪
第6位:化粧品成分検定
日本化粧品検定とは異なる法人が主催している検定です。身の回りにあふれる化粧品に記載されている全成分の情報を読み解けるように導く検定です。自ら目的にあった化粧品を正しく選択できるようになります。
・化粧品の成分に焦点をあてて化粧品の接客ができる!
・ドラックストア勤務であれば、市販薬も化粧品も『成分マスター』になれる!

6位からは、時間はかかっても
いずれ取得したいなと思う検定です!
登録販売者の試験勉強の際、カタカナの成分名に最初は驚いたのですが、覚えてみると楽しく、日常の市販薬の選定にも使えることが嬉しかったです。化粧品に関しても、成分を理解して選べるようになりたいので今後取得したい検定のひとつです。
第5位:メディカルアロマ検定
統合医療の基礎知識から精油の安全性、有用性、心身への作用や使い方などを習得できます。安全なアロマテラピーの利用法や役立て方などの知識の修得を証明する資格です。
ドラックストア勤務であれば、市販薬以外の接客でも香りの作用に沿ったご案内ができ顧客化につながる!
メディカルアロマセラピーでは、香りが脳に伝わりそこから心に作用する仕組みを活用しているそうです。香りの癒し効果と精油成分の薬理作用でさまざまな不調に効果を示すことが期待できます。
私自身、香りの効果は高いと思っています。登録販売者試験の当日も、ハンカチにアロマオイルを垂らしたものを嗅いでから試験に臨んだり、勉強中も睡眠前もアロマオイルを活用したりしていました。しかし、メディカルアロマとなるとまた違った切り口で、新たな知識が得られそうですね。
第4位:サプリメントマイスター検定
健康食品・サプリメントを「購入」「説明」「販売」する方に役立つ資格です。
サプリメントの選定で適切なご案内ができる!健康食品と薬は似ているものだと思っているお客様が多いため、頼りにされる✨
健康食品素材の知識を習得できます。セルフメディケーションやドラッグストアでの商品説明などに活用できます。
サプリメントはほぼ無知の私ですが、「もしもドラッグストアで働くのならば、(登録販売者を取得後)薬学検定とサプリメントマイスター検定を受験すると良い」というお話を聞いたことがあり、それを聞き一気に取りたくなりました。確かにドラッグストアでは、サプリメントも多数扱っていますものね。
自分や家族のためにサプリメントを選ぶ際にも役に立ちます。
第3位:薬膳・漢方検定
この検定は、
- いつもの食材で薬膳レシピが作れる
- 漢方の基本理論を分かりやすく学べる
- ちょっとした気になる症状に役立つ知識が得られる
薬膳(中医学に基づいた食事のこと)と漢方について学ぶことができます。
・接客中に、症状に合わせたおすすめの食べ物や養生法がお伝えできる!
・漢方薬局で働くのであれば、知識を存分に生かせる!
ちなみに、著者はこの検定を一度受験し不合格でした(笑)ほとんど何も勉強できないまま受験したので、いつかリベンジしたいです。
受験した感想としては、五行色体表をしっかり覚え、それに食材を当てはめていくと合格できるのではないかなと感じます。
\五行色体表を暗記で覚える方法は↓/
第2位:薬学検定
薬学の知識レベルを上げる検定です。市販薬やサプリメント、保健機能食品の基本問題から、1級では医療用医薬品や食品と薬の飲み合わせまで学ぶことができます。
登録販売者として仕事をする方すべてに役立つ!知識の底上げができる!
1~4級がありますが、登録販売者の資格を持っている人はまず2級or3級がおすすめだそうです。受験方法は、在宅受験と団体受験で分かれています。
登録販売者の資格を取得後、さらに勉強をしたい方にはピッタリの資格です。今後登録販売者として働くのであれば、飲み合わせや更に上の知識はぜひ欲しいところですね。
第1位:中医学検定
生活の中で役立つ「中国医学」に関する知識が習得できます。自分で「中国医学」を学び、体系的な知識の獲得を目指します。
・中医学に沿った養生法がお伝えできる!
・漢方薬局で働くのであれば、知識を存分に生かせる!
また、2級では「中国医学」に関する専門的な知識をもとに正しい診断が出来るレベルまで目指すことができます。
比較的新しい検定で、2023年6月に第一回目の検定が初めて実施されました。オンライン受験です。
私は以前登録販売者の試験のために、Twitter(現X)を開設したのですが、先輩の登録販売者で中医学に興味を持っておられる方はとても多い印象です。登録販売者だけでなく、中医師の先生のTwitter(現X)などもフォローすると中医学が身近に感じられて面白いですよ。
実際に私もTwitterの先生や先輩方のつぶやきから関心が持て、この第一回の検定を受験することにしました。覚えることが沢山ですが、受験が楽しみです。受験した際には、また記事を書きます!
追記:受験して、あと2点足らず不合格でした( ノД`)でも勉強はとても楽しかったです。受験の感想はこちらからご覧いただけます!↓
次の検定日は2024年6月23日です!
まとめ:好きなものにチャレンジするべき!
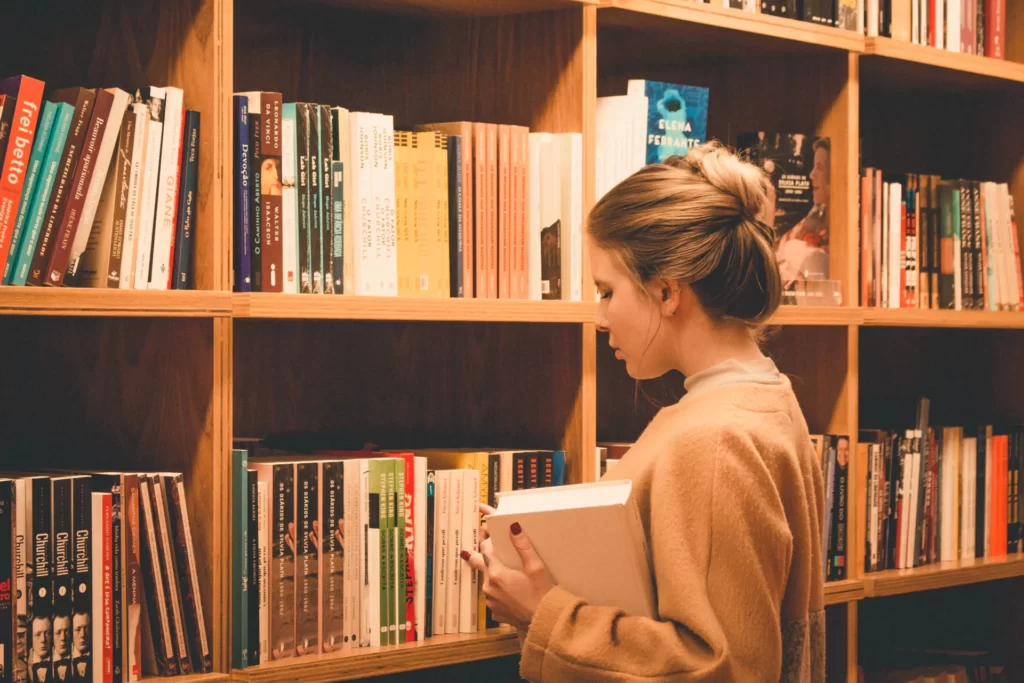
今回は、個人の裁量で勝手に登録販売者が今後取得したい資格・検定ランキングを作成いたしました。まだまだ私の知らない資格・検定もあると思います。
興味関心を持って、好きなことにチャレンジすることはとてもいいことです。どんなジャンルであれ、頑張っている人は素敵です。知識をつけて、役立てていきましょう!
登録販売者の皆さん、資格・検定を取りたい皆さん、何かを頑張っているみなさん、一緒に頑張りましょう!